| 2012年3月8日(木) |
| 【出版情報】「農業経営研究の軌跡と展望」(徳田・内山教員) |
 |
農業経営を取り巻く急激な環境変化を踏まえた,農業経営研究の近年の動向と今後の課題について,日本農業経営学会がまとめたものです。
61名の執筆者が,研究の評価および展望を記していますが,当講座からは徳田教員が「園芸経営研究」について,内山教員が「個別経営に関する研究」について,それぞれ執筆を担当しています。(もどる)
【出版データ】日本農業経営学会編・津谷好人責任編集『農業経営研究の軌跡と展望』農林統計協会(2012年2月),5,000円+税 |
|
|
| 2012年2月23日(木) |
| 卒業論文発表会開催(2/22) |

(発表会にて)

(ポスターセッション) |
卒業論文発表会が開催され,講座所属学生によるプレゼンテーション(午前)と,資源循環学科所属学生によるポスターセッション(午後)が開催されました。当講座では,卒業予定の10名による研究発表が行われました。(もどる)
[卒業論文発表一覧]
・市川 直志「認定農業者制度の見直しに関する考察―カナダ・オンタリオ州の農業経営成長支援プログラムを題材に ―」
・田中 佑治「産地銘柄牛生産者をめぐる環境変化と今後の展望―伊賀牛を事例として―」
・小川 理恵「コミュニティ・レストランの役割と展望―三重県内で地産地消に取り組むレストランを事例として―」
・瀬古 健司「養殖業者と企業の連携における問題点と課題-三重県尾鷲市のマダイ養殖を事例に-」
・新美 茉夕「鳥羽市による「エコツーリズム」の形成過程とその特徴」
・渡邊 顕吾「琵琶湖の外来魚駆除における漁業者の役割」
・尾崎貴哉「みかん産地に立地する直売所の顧客の特徴と購買行動―南伊勢町の直売所「土実樹(つみき)」を事例に―」
・島田 由貴「地域ブランド推進による地域活性化―三重県の農水畜産物と食品に着目して―」
・楢井 淳一「三重なばなの現状と課題―ブランド戦略を中心として―」
・戸倉 大樹「国内養蜂業の現状と今後の課題」 |
|
|
| 2012年2月10日(金) |
| 農業経営成長支援プログラム調査(カナダ/内山教員) |

(聞き取り調査の様子) |
科研費(挑戦的萌芽)「企業的農業経営の新たな育成手法の開発―経営ステージを踏まえた認定農業者支援方策」(代表:内山教員)の調査研究の一環で,カナダ・オンタリオ州における農業経営成長支援プログラムの概要および運営実態に関する現地調査を実施しました。
オンタリオ州農業省や関係機関に対する聞き取り調査,農業者向けワークショップの視察・参加などを行いました。(もどる) |
|
|
| 2012年1月31日(火) |
| 荒廃農地の復元ボランティア(講座学生) |

 |
亀山市加太地区の「北在家環境保全営農組合」
による荒廃地復元の取り組みに,学生ボランティアとして当講座より学生2名(山藤君,麻生君)が参加しました。
草刈機をつかって背丈以上の笹を刈り倒し、焼却するために笹を集める作業を体験しました。昼食や休憩の時には、地元の人と参加した動機などについてはなしてもらう等の交流も行いました。(もどる)
|
|
|
| 2012年1月17日(火) |
| 【出版情報】「北米における穀物集荷業者の動向と展望」ほか |
 |
日本農業経営学会発行『農業経営研究』に,下記2論文が掲載されました。
内山論文は,全米最大の大豆・とうもろこし生産地であるアイオワ州の穀物集荷業者に対する調査結果,甲斐論文は同じくアイオワ州において新規参入者と離農予定者をマッチングさせるプログラム「Farm-On」の分析結果をそれぞれ示しています。また,甲斐論文は卒業論文を取りまとめたものです。(もどる)
【出版データ】
・内山智裕・西嶋亜矢子「北米における穀物集荷業者の動向と展望―米国アイオワ州における穀物エレベーター調査から―」(pp.1-11.)
・甲斐理紗・内山智裕「米国における農業経営継承支援事業の実態分析-米国アイオワ州の事例からの含意析出-」(pp.133-138.)
(『農業経営研究』49(3),2011年12月所収) |
|
|
| 2012年1月13日(金) |
| オランダから米国への移住酪農家調査(1/3-8内山教員) |

(大型牛舎の様子:ウィスコンシン州) |
オランダを初めとした欧州の酪農界では,ミルククォータの廃止や環境規制の強化など,酪農経営の拡大が困難になりつつあり,酪農家が国外に移住する動きがあります。一方,豊富な土地資源をもつ米国は経営拡大の余地は大きいものの,一部の州では外国籍の個人・企業による農地取得を規制しています。
本調査では,このような国境を越えた農地取得行動に着目し,全米2位の酪農州であり,外国籍の農地取得を規制しているウィスコンシン州において,実際に移住をしたオランダ人酪農家を訪問し,移住の経緯や現在の経営概況,農地取得規制の影響などについて聞き取り調査を行いました。(もどる) |
|
|
| 2011年12月26日(月) |
| 「社会科学チュートリアル」発表会を開催(12/14学部2年生) |

(学生発表と質疑応答のようす) |
「社会科学チュートリアル」に参加している学部2年生が4つの班に分かれ,10月・11月に実施した農家訪問やグループワークによる成果を発表しました。
発表会には,訪問先の農家や三重県農村女性アドバイザー,普及指導員などの方々にもご参加きし,学生の発表に対する質疑応答などを行いました。(もどる) |
|
|
| 2011年12月7日(水) |
| 三重大学駅伝大会に2チーム参加(12/4講座学生・教員) |

 |
12月4日(日)に開催された第5回三重大学駅伝大会に,講座有志が出場しました。
留学生を含む学生11名,教員2名が2チームに分かれて出場しました。うち,「私情軽罪」チームは出場40チーム中8位の好成績を収めました。もう1チーム(「Yes国際」チーム)は,33位でした。
雨天のため1日順延となったうえ,時折小雨のぱらつく天気でしたが,チームの全員が完走しました。(もどる) |
|
|
| 2011年11月25日(金) |
| 「高田高校SPP」現地学習・成果発表会(石田・山田教員) |

(観測体験のようす) |
SPPとはサイエンス・パートナーシップ・プロジェクトの略で,学校と大学等との連携により、科学技術、理科・数学に関する観察、実験、実習等の体験的・問題解決的な学習活動を行うものです。
7月30日~31日にかけて三重大学練習船勢水丸を用いて、伊勢湾上で洋上観測体験を行いました。高田高校の2年生10名が参加し、水質、底泥、底棲生物観測を行いました。また、11月19日には得られたデータや事前・事後学習の成果をまとめた発表会が行われ、活発な議論が行われました。(もどる) |
|
|
| 2011年11月18日(金) |
| 「ワーク・ライフ・バランス」ワークショップ参画(11/12学部3年林さん・堀部さん,内山教員) |
 |
三重県/三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」主催の「男女共同参画フォーラム」において,ワークショップ「仕事も家庭もどちらも大切~ワーク・ライフ・バランスの観点から~」が開催されました。このワークショップに,当講座より,学部3年生の林美緒さんと堀部将明さんがパネリストとして,内山教員がコーディネーターとして参画しました。(もどる) |
|
|
| 2011年11月10日(木) |
| 「社会科学チュートリアル」現地実習2(11/9学部2年生) |

 |
「社会科学チュートリアル」の現地実習の一環として,亀山市のTUMUGI舎を訪問し,さつまいもの収穫作業,食品加工作業などを体験しました。
当授業では,三重県農村女性アドバイザーのご協力を頂き,鈴鹿・亀山地区を中心に,食料・農業・農村に関する実習を設定しています。今回の実習は10月に続き2回目です。今後は,これらの実習を踏まえて,食料・農業・農村をめぐる問題についてグループワークを進めていきます。(もどる) |
|
|
| 2011年10月31日(月) |
| 「社会科学チュートリアル」現地実習(10/26学部2年生) |

(収穫作業の様子) |
「社会科学チュートリアル」の現地実習の一環として,鈴鹿市の河北水耕園を訪問し,ねぎの定植・収穫・出荷調整作業を体験しました。
当授業では,三重県農村女性アドバイザーのご協力を頂き,鈴鹿・亀山地区を中心に,食料・農業・農村に関する実習を設定しています。(もどる) |
|
|
| 2011年10月21日(金) |
| 欧州調査(科研)「村落共同体と市民社会の連帯の日欧比較」(石田・波夛野教員) |
 |
農村地域再生の担い手として集落の自治会やNPOをはじめとする様々な組織が活動していますが、その成果を自分たちのもとに蓄積するための適切な事業形態についての法的整備は遅れています。
一方で、欧米では、ワーカーズコレクティブ(事業組織の構成員間に雇用被雇用の関係がなく、労働者が自分たちのために働き、自分たちで利益を分配する形態)に適した形態が国ごとに設定され活発に活動しています。
今回は特に、農村地域において、住民が自分たちのために働くことを通じて地域社会の維持・再生に貢献している事例を現地で探索しました。
写真は、村のゲーム同会が運営する喫茶+レストラン+農産物直売所とその代表者です。(もどる) |
|
|
| 2011年10月14日(金) |
| 米国4州の農地取得規制調査(9/20-30内山教員) |

(農場風景:ウィスコンシン) |
日本では,農地法の改正などにより,農地取得規制の緩和が進んでいます。日本に独特の規制を緩和する動きと捉えられがちですが,海外をみると,例えば米国の一部の州では企業や非居住外国人による農地取得が規制されています。
今回は,オクラホマ・ミネソタ・アイオワ・ウィスコンシンの4州を訪ね,これらの規制の背景・効果・展望などについて聞き取り調査を実施しました。(もどる) |
|
|
| 2011年10月7日(金) |
| 【出版情報】「アグリビジネスの新たな企業戦略と我が国の戦略的対応―北米地域に着目して-」(内山教員) |
|
農林水産政策科学研究委託事業(農林水産省農林水産政策研究所)による標記研究の内容紹介が,『農林水産政策研究所レビュー』に掲載されました。
特に,外国籍(外国企業・非居住外国人)による農林地取得規制について,現状と今後の展望を示しています。本文はこちら(外部サイト)で公開されています。(もどる)
【出版データ】内山智裕「アグリビジネスの新たな企業戦略と我が国の戦略的対応―北米地域に着目して-」『農林水産政策研究所レビュー』43,pp.12-13.,
2011年9月. |
|
|
| 2011年10月5日(水) |
| 【出版情報】「柑橘園地基盤整備の効果と農業構造再編」(徳田教員) |
 |
日本農業経営学会発行『農業経営研究』に,下記論文が掲載されました。
労働集約性が高い果樹農業では,機械化の促進等による省力的な技術体系の確立が課題ですが,その方策の1つとして園地の基盤整備に着目し,ハード面の整備に加えて担い手への園地の集積や団地化を行うことが重要であることを明らかにしました。(もどる)
【出版データ】徳田博美「柑橘園地基盤整備の効果と農業構造再編」『農業経営研究』49(2), pp.51-56., 2011年9月. |
|
|
| 2011年10月3日(月) |
| 「社会調査演習」現地調査を実施(9/27-29学部3年生) |

(発表会の様子) |
9月27日~29日の3日間、「社会調査演習」で3年生20名、4年生1名を連れて三重県志摩市に入りました。
志摩市は今流域の保全をベースに「稼げる、遊べる。学べる、里海創生計画」を策定中で、今回全面的にサポートしてくれました。学生もがんばり、21名の学生が5班に分け全部で約20件のヒアリング、現地見学を体験し、最終日には5つの班が「若者の提案」を市の10人ほどの職員の前で発表し、職員からコメントとアドバイスを受けるという時間を持ちました。後で「良い提案をしてもらった。できれば市の正規事業につなげたい。」とのコメントをもらうほどで、予想を上回る成功になりました。(高山記)(もどる) |
|
|
| 2011年9月12日(月) |
| 日本農業経営学会研究大会を開催(9/8-11) |
|
平成23年度日本農業経営学会研究大会が,上記日程で三重大学をメイン会場として開催されました。9/9には地域シンポジウム「地域の農業と地場産業の連携による地域活性化」を開催しました。その他,エクスカーション,大会シンポジウム,分科会,特別セッション,個別報告などが実施されました。
地域シンポジウムの様子は,三重大学広報室ブログに掲載されています。(もどる) |
|
|
| 2011年9月9日(金) |
| 【出版情報】『次世代土地利用型農業と企業経営』 |
 |
家族農業経営から企業経営への成長,他産業からの企業の農業参入に焦点を当てた研究書です。日本農業経営学会が平成21年度および22年度に開催したシンポジウムの成果をとりまとめたものです。
内山教員は,第Ⅰ部第4章「農業における「企業経営」と「家族経営」の特質と役割」の執筆を担当しています。(もどる)
【出版データ】日本農業経営学会編『次世代土地利用型農業と企業経営―家族経営の発展と企業参入―』養賢堂2011年(3,400円+税) |
|
|
| 2011年9月6日(火) |
| CSA農家調査・NHK取材(8/29~31波夛野教員) |

(農家取材の様子) |
放射能汚染の広がりの中でどのように農家、消費者の関係を構築するかについて農業倫理の側面から考えるために、福島、茨城、神奈川の農家を訪ねてきました。
同様の目的で、先日、波夛野教員を取材したNHK報道局のスタッフも神奈川のCSA(Community Supported Agriculture)農家で合流しました。番組名は、NHKスペシャル「新生日本②」~”食”の安心を取り戻せ~。73分で、2011年10月22日(土)夜放送予定です。(もどる) |
|
|
| 2011年9月2日(金) |
| ビジネス能力検定に受験者全員合格(学部3年生) |
|
今年度前期の「循環社会システム学演習」(内山教員担当)では,ビジネス能力検定合格をめざした勉強を行い,7月3日の第30回検定試験を団体受験しました。
この度結果が通知され,3級に13人,2級に3人が合格しました。いずれも受験した学生全員が合格しました。
当講座では,今後も講座学生のキャリア支援の一環として資格取得を応援していきます。(もどる)
【参考】ビジネス能力検定サイト |
|
|
| 2011年8月30日(火) |
| 「直売所甲子園2011」一次審査を実施(8/18~25講座学生) |


(審査の様子) |
8月18日~25日,「直売所甲子園2011」にエントリーされた三重県内6か所の農産物直売所を講座学生計6名が訪問し,一次審査を実施しました。
「直売所甲子園」は農産物直売所の日本一を決定する大会で,一次審査は各地の農学系大学生が担当しています。(もどる)
【参考】直売所甲子園2011サイト |
|
|
| 2011年8月26日(金) |
| 「漁業経営と今後の課題」講演(8/24常教員) |
|
8月24日に津市プラザ洞津で開催された「農商工連携を促進す る“農商工連携事業プロデューサー”研修会」(三重県中小企業団体中央会主催)にて、常教員が「漁業経営と今後の課題」を題とする講演を行いました。(もどる) |
|
|
| 2011年8月11日(木) |
| 「食と農を取り巻く情勢と地域農業の展望」講演(内山教員) |
|
8月10日に津市で開催された「津地域 食と農の活性化研修会」(主催:津市農業委員会・三重県津農林水産商工環境事務所)」にて,「食と農を取り巻く情勢と地域農業の展望」と題した講演を行いました。
講演会の様子はNHKの地域ニュースでも取り上げられました。(もどる) |
|
|
| 2011年8月1日(月) |
| 三重南紀地区で柑橘農家の実態調査(徳田教員) |
 |
7月7~8日,14~15日,28日に三重県内の主要な柑橘産地である南紀地区において,柑橘農家の聞き取り調査を行いました.この調査は,JA三重グループからの研究助成に基づいて行っている「三重県内の柑橘産地における産地振興戦略の解明」の一環として行っているもので,農家の栽培管理や果樹園の流動化などについて調査しました.この調査に基づいて,柑橘農家の規模拡大の可能性とその方策について検討していきます.(もどる) |
|
|
| 2011年7月25日(月) |
| JAグループ三重「食・農・いのちの市民講座」にて講演(高山教員・波夛野教員) |
 |
7月23日に津市の橋北公民館にて,JAグループ三重「食・農・いのちの市民講座」が開催され,当講座から高山教員と波夛野教員が下記講演を行いました。
今後も同じ内容の市民講座が四日市,松阪,鈴鹿の3会場でも開催されます。参加申込み方法等については,下記リンク(学外)をご参照ください。(もどる)
【当講座教員の講演タイトル】
・高山進「いのちをつなぐ時代への扉~生物多様性と大震災~」
・波夛野豪「いのちと土の循環~有機農業の世界~」
【参考】JAグループ三重,食・農・いのちの市民講座案内パンフレット |
|
|
| 2011年7月22日(金) |
| 「循環社会システム学演習」にて製茶工場を訪問(7/20学部3年生) |

(工場見学)

(お茶の淹れ方)

(班別発表会) |
「循環社会システム学演習」(内山教員)に参加している3年生16名と4年生有志3名で,鈴鹿市にある製茶工場「ささら」を訪問しました。
近畿圏随一の工場設備の見学,「おいしいお茶の淹れ方」を学ぶなどした後,班別にSWOT分析を行い,製茶業のとるべき戦略などについて,生産者の方,三重県農村女性アドバイザーの方を交えながら議論を進めました。(もどる)
【参考】株式会社ささら |
|
|
| 2011年7月19日(火) |
| 「漁村への若壮年層のUターン・Iターン促進のための“希望ある地域づくり”の課題と政策提言」プロジェクト採択(常教員) |
|
当研究プロジェクトは、漁村地域の陸上産業が不振を続ける状況下で,Uターン,Iターンの促進をはかるために必要な社会的・客観的条件と主体的な契機を「外部者」(=都市生活者)の視点から抽出し、その地域に存在する潜在的資源の発見と魅力を引き出し、条件整備のための政策提言を行うことを目的としています。(もどる)
【採択データ】福井県「県民参加による県立大学地域貢献研究推進事業」採択課題(研究代表者:長谷川健二(福井県立大学)分担:常(三重大学)分担:加瀬和俊(東京大学)) |
|
|
| 2011年7月14日(木) |
| 「黒潮流域圏における生物資源と環境・食文化教育のための共同利用拠点」スタート(常教員) |
|
三重大学生物資源学部・研究科附属練習船勢水丸が標記の利用拠点として文部科学省に認定され、今月から事業が本格的にスタートします(平成27年3月31日までの5年間)。
当事業は、地域の食文化と食環境の教育を柱とする教育プログラムを開発し、全国の練習船を保有していない大学・高等専門学校等にも勢水丸に乗船する機会を提供し、黒潮流域の漁村との交流拠点として活用し、「地域から学び、世界に誇れる」先進的な環境知識と行動力、社会性を兼ね備えた学生を社会への排出に寄与しようとするものです。
常教員は,当事業の地域の食文化教育を担当します。(もどる) |
|
|
| 2011年7月11日(月) |
| 日本農業市場学会2011年度大会で研究報告(7/3徳田教員) |
|
7月2-3日に鹿児島大学で,日本農業市場学会2011年度大会が開催されました。その中で徳田教員が,「合併農協における販売事業の再編過程-JAフルーツ山梨を事例として-」というタイトルで,広域合併農協における販売事業の再編実態について,ぶどう,ももをはじめとする多様な果実品目を有し,全国一のもものブランド力を持つ地区からぶどうの観光農業で全国一の知名度を有する地区まで多様な特徴を持つ地区で構成されているJAフルーツ山梨を事例として,その特徴と課題について個別報告を行いました。(もどる)
【報告データ】徳田博美「合併農協における販売事業の再編過程-JAフルーツ山梨を事例として―」2011年度日本農業市場学会大会個別報告,鹿児島大学,2011年7月3日 |
|
|
| 2011年7月7日(木) |
| ビジネス能力検定試験を学内実施(7/3学部3年生) |
|
「循環社会システム学演習」(内山教員担当)では,ビジネス能力検定合格に向けた勉強をしてきましたが,7月3日に学内にて検定試験を実施しました。
授業に参加した学生(学部3年生)のうち13名が3級,3名が2級を受験しました。
学内での試験実施は今年で5回目です。試験の結果は8月下旬に判明する見込みです。(もどる)
【参考】ビジネス能力検定 |
|
|
| 2011年7月4日(月) |
| 中部農業経済学会2011年度研究大会にて発表(6/18徳田教員) |
|
6月18日に岐阜大学において,中部農業経済学会の2011年度研究大会(第81回研究発表会)が開催されました。その中のシンポジウム「農政転換期における水田農業経営と野菜産地再編の課題」において,徳田教員が「輸入に対抗した野菜産地における生産支援システムの導入と担い手形成」というタイトルで,1990年代後半以降に増加した野菜輸入に対抗した野菜産地の取組の特徴と成果等について報告しました。(もどる)
【発表データ】
徳田博美「輸入に対抗した野菜産地における生産支援システムの導入と担い手形成」中部農業経済学会第81回研究発表会シンポジウム「農政転換期における水田農業経営と野菜産地再編の課題」報告,岐阜大学,2011年6月18日. |
|
|
| 2011年6月30日(木) |
| 米国カリフォルニア州における園芸農業生産・流通実態調査(徳田教員) |

(イチゴの収穫作業) |
6月6~12日の日程で世界的な園芸農業地帯である米国カリフォルニア州で園芸農業生産・流通に関する実態調査を行いました。
この調査は,受託研究「アグリビジネスの新たな企業戦略と我が国の戦略的対応」(農林水産省農林水産政策研究所)の一環として昨年に引き続いて実施したもので,今年度は,育苗から肥培管理,収穫といった一連の農作業の受託会社の調査など,分業化の進展している生産体制や近年,生産が著しく伸びているイチゴの生産会社などを調査するとともに,野菜の生産コストなどのデータを収集しました。(もどる) |
|
|
| 2011年6月28日(火) |
| 【出版情報】「企業の農業参入と地域農業の関係に関する一考察」など(徳田教員・内山教員) |
 |
地域農林経済学会発行『農林業問題研究』に当講座から下記2論文が掲載されました。外資系企業による農業参入と地域農業の関係に関する論考,米国における外国企業による農地取得に対する規制の動向など,国境を越えた企業行動が農業・農地に与える影響について分析しています。(もどる)
【出版データ】
・徳田博美「企業の農業参入と地域農業との関係に関する一考察―長崎県五島市のD社関連法人・Iファームの参入を事例として―」pp.144-149.
・内山智裕「米国における外国企業の農地所有規制の現状と含意」pp.72-77.
(『農林業問題研究』47(1),2011年6月所収) |
|
|
| 2011年6月3日(金) |
| 【学内情報】海外農業研修説明会のお知らせ(6/22) |
|
(社)国際農業者交流協会が実施する海外派遣農業研修の説明会を下記の通り開催します。学部・学科・学年を問わず,どなたでも自由に参加できますので,お気軽にお越し下さい。
今回説明に来られる三浦氏は,資源循環学科卒業生(平成16年度卒)で,同事業でスイスで1年間研修を行いました。また,当講座では過去7年で5名の学生・卒業生が同事業に参加しています。(もどる)
[日時]6月22日(水)12:10-13:00
[場所]生物資源学部475室(4F)
|
|
|
|
|
| 2011年5月26日(木) |
| 【研究】アグリビジネスの新たな企業戦略と我が国の戦略的対応(内山・徳田教員) |
|
農林水産省農林水産政策研究所「農林水産政策科学研究委託事業」に,標記課題が採択されています。
2009年度より3ヵ年の研究で,本年度が最終年度となります。国際的な穀物・青果物流通の動向や,農業投資ルールのあり方などについて調査研究を進めています。(もどる)
【採択データ】
受託研究「アグリビジネスの新たな企業戦略と我が国の戦略的対応―北米地域に着目して―」<代表:内山智裕,分担:徳田博美(以上三重大学),分担:八木洋憲(東京大学)>(農林水産政策科学研究委託事業) |
|
|
| 2011年5月23日(月) |
| 講座新入生歓迎会(縦コン)開催(5/17) |
|
恒例の講座新入生歓迎会(縦コン)を開催しました。学生・教員計60名余が参加し,今春に講座配属となった学部2年生と,大学院新入生を歓迎しました。新たに講座に所属することになった皆さんが,卒業・修了まで充実した学生生活を送ることを祈念します。(もどる) |
|
|
| 2011年5月17日(火) |
| 【出版】『ドイツ協同組合レポート 参加型民主主義―わが村は美しく―』(石田教員) |
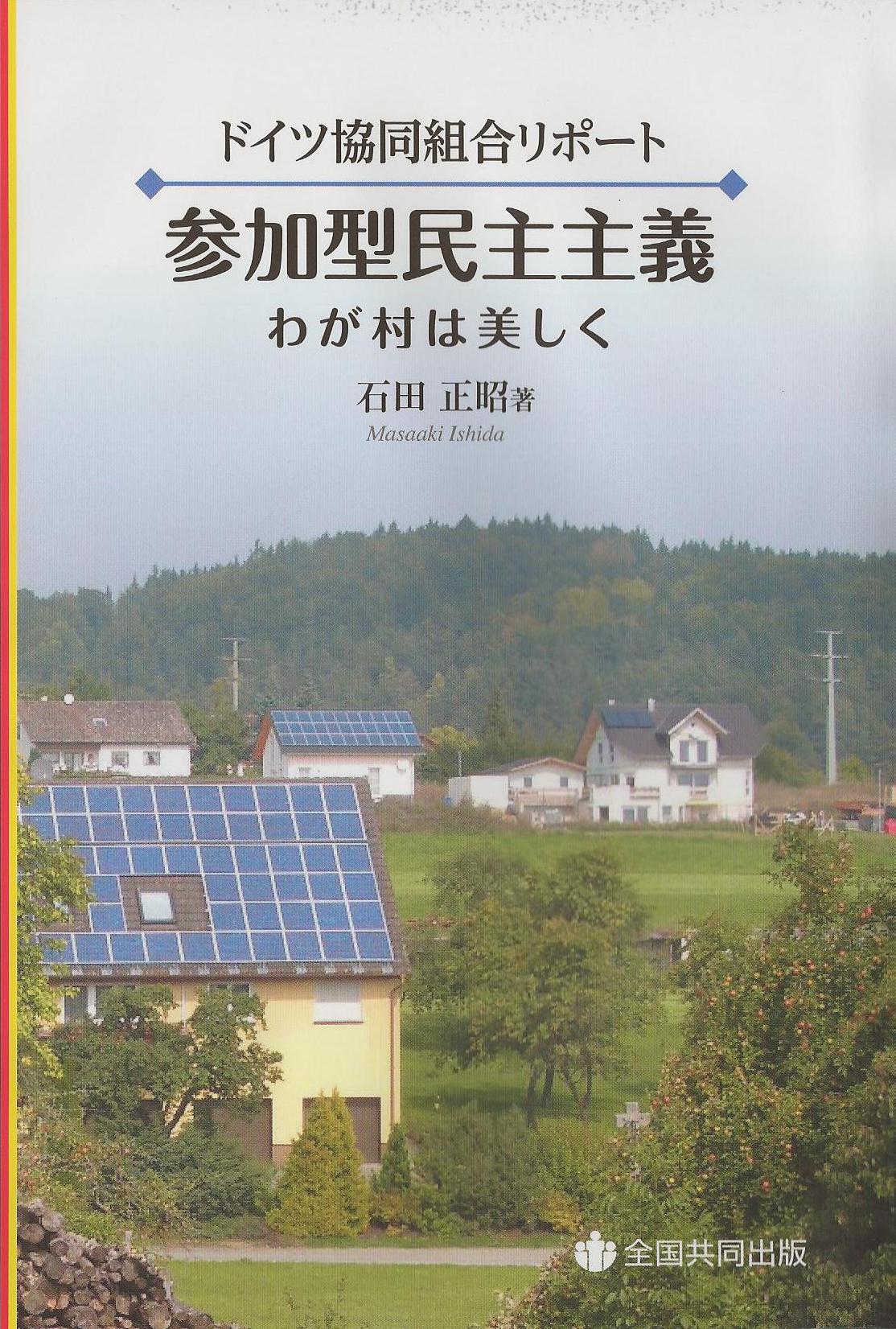 |
地域社会(コミュニティ)を元気にするための公共的活動を担う人々が,どのような集団や組織をつくり,どのような活動を行っているのか,また,そうした公共的活動に農業協同組合や協同組合銀行などの伝統的な協同組合がどのようにかかわっているのかという問題を,ドイツを事例に検討したものです。
科学研究費補助金(基盤B)「農村社会開発におけるソーシャルガバナンスの研究―美しい村づくりの日独比較―」(研究代表:石田教員)の研究成果の一部です。(もどる)
【出版データ】石田正昭『ドイツ協同組合リポート 参加型民主主義―わが村は美しく―』全国共同出版,2011年5月,p.115. (ISBN:978-4-793-41103-8) |
|
|
| 2011年5月13日(金) |
| 「簿記会計演習Ⅰ」が学部教育表彰(5/11 内山教員) |
|
当講座開講科目「簿記会計演習Ⅰ」が平成22年度後期「授業改善のためのアンケート」の総合満足度で最も高い評価(アンケート回答数46名以上の講義の部)を受けたことから,教育表彰されました。
生物資源学部では、教育内容・方法の改善と向上のためのFD(Faculty Development)活動を積極的に行っています。その一環として、学期ごとに各授業科目について学生による授業評価アンケートを実施,学生評価の高い授業をおこなった教員に対して表彰をおこなっています。(もどる) |
|
|
| 2011年5月9日(月) |
| 【研究】2011年度科学研究費採択 |
|
当講座では,今年度の科学研究費補助金・助成金の交付課題として,以下の5件が採択(内定)されました。科学研究費は,学術研究の発展を目的とする競争的研究資金で,文部科学省・日本学術振興会による審査を経て採択されるものです。(もどる)
・「食・農・環境の仕事おこしによる地域再生―村落共同体と市民社会の連帯の日欧比較―」(新規,基盤B,代表:石田教員)
・「CSAによる生産者と消費者の連携に関する研究―地産地消の次段階的展開―」(継続,基盤C,代表:波夛野教員)
・「技術体系変革下における果樹農業構造再編の展開方向の解明」(継続,基盤C,代表:徳田教員)
・「企業的農業経営の新たな育成手法の開発―経営ステージを踏まえた認定農業者支援方策―」(新規,挑戦的萌芽,代表:内山教員)
・「ファーム・ファミリー・ビジネス論による新たな農業経営学の構築―臨界点に着目して―」(新規,若手A,代表:内山教員)
|
|
|