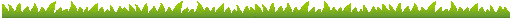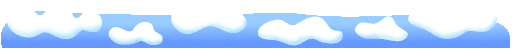
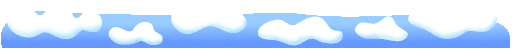
このページは、どうでもいいと思っていましたが、いろんなところから反響があり、それなりに読んでいただいているということがわかってきました。ぼちぼち、日々の生活を書いていきたいと思っています。
12月某日 仕事納め カレンダーの関係で、例年より1日はやい仕事納めとなりました。また、カレンダーの関係で、これまでになく長い正月休みとなります。2024年もいろんなことがありました。すべきことをこなすのが精一杯なところもありつつ、けっこう手抜きもしたなあという感じです。もうちょっとできたよねって思うこともたくさんありました。まあ、それでも、過去にはもどれませんので、2025年にむけて頑張るしかないという感じです。数えてみれば、大学に来る日も、60日を切っており、きっと3月末までは、あっという間な感じです。皆様、よいお年をお迎えください。
12月某日 卒業生 研究室のOBが、お菓子をたくさん買って、後輩に頑張ってもらおうと、たずねてくれましたが、在校生が誰もいない。12月の終わりは、かつては、研究室がにぎやかな時期でありましたが、最近は、そんなこともなく、ゆったりと時が流れています。
12月某日 高大連携 これが高校生のPCR実習の最後でした。ちょっと前日に体調不良で、準備が十分にできず、直前になってプライマーがないのに気づき、あわてました。保存場所を変えていたのをすっかりと忘れていました。
12月某日 セルラーゼ研究会 沖縄で開催された第34回セルラーゼ研究会に参加ました。さすがに、沖縄は暖かいですね。コロナ禍で、しばらく休止しておりましたが、再開して、どうなるかと思いましたが、かつてのようなセルラーゼ研究会で、ほっとしました。これからも続いてくれると嬉しいですね。おみやげに、モノレールグッヅを購入しようと思ったのですが、那覇空港駅では販売しておらず、残念でした。県庁駅までもどってくださいと言われましたが、もどる元気がでませんでした。
12月某日 きき酒訓練 赤ワインをしたら、白ワインもしないわけにはいかない。チャルドネ、ソービニオンブラン、リースリングと、3つのブドウの品種の飲み比べをした。家飲みでは、白は、ほぼシャルドネだけどね。意外とソービニオンブランもいける。
12月某日 三重大学開学75周年記念行事「アート&サイエンスフェスタ」 フェスタにて、「発酵と食品」という講演を行った。三翠大ホールで、話しをするのも、多分、これが最後かな。会場はでかいが、それでも、けっこう人には目がいくもので、懸命にメモをとりながら聴いてくれる人もいたので、まあ、よかったかなという印象でした。
12月某日 歴史的建造物めぐり 大阪の綿業会館、中之島の大阪図書館、大阪中央公会堂を見学した。綿業会館は、リットン調査団が来た建物でもあり、関東大震災後、大阪が日本の経済の中心だったことを偲ばせる、豪華なつくりがみものであった。グリルでのランチも楽しめた。大阪図書館では、ガイドツアーに参加して、いろいろなことを教えていただいた。本が珍しい時代にあって、私費を投じてつくられた図書館、当時は利用も有料だったとか。日銀の建物との調和を意識した設計など、知らないことがたくさんあった。図書館内のカフェを満喫し、おおとりは、大阪中央公会堂の見学と、夜のプロジェクションマッピング。ライトアップやイルミネーションで輝く中之島にあって、ひときは、輝く公会堂のプロジェクションマッピング。いい時間を過ごす事ができた。
12月某日 工場見学の引率(その1) 県内の医薬品の生産工場を、学生の引率で見学しました。研究所がちょっとうらやましい感じです。企業の研究室や、製造プラントを見学することは、とっても勉強になるかと思います。見学を引き受けていただいている企業さんには、大学教育に参画していただき、本当に感謝しかありません。
12月某日 イルミネーション 今年も三重大学の学内イルミネーションが点灯しました。日暮れが早いので、イルミネーションがあるおかげで、道が明るくていいです。今年は、国道23号線側にもイルミネーションが点灯し、大学をアピールしています。
12月某日 オペラ 名古屋まで「椿姫」の演奏会形式の舞台を見にでかけました。ソプラノが三重大学のOBと知り、気合いをいれて聴きました。管弦楽はいいですね。
11月某日 カマンベールチーズ 食品発酵学のチーズの授業のなかで、近年のカマンベールチーズの認知機能への改善効果についての報告を紹介した。近所のスーパーで、思わず、カマンベールチーズを買ってしまった。最近、忘れることが多いが、余計な事を考えずにすむので、忘れっぽいことは、素敵なことかもしれない。
11月某日 きき酒訓練 赤ワインのぶどうの品種は、わかるようになってほしいと、カベルネソービニオン、メルロー、ピノノアールの3つの赤ワインぶどう品種のワインを飲み比べた。個人的には、ピノノアールが好きだけど。
11月某日 侍ジャパン 決勝にいたるまで、横綱相撲だったが、最後の最後にだめだった。おめでとう台湾。やはりいい投手だと簡単には打つことは難しい。
11月某日 京都 嵐山にでかけた。紅葉の見ごろには少し早かった。それでも木々は色つきかけていた。それにしても外国人の多いこと、ちょっと驚いた。こんなに海外から京都に来ているのかと思った。聞こえる日本語は、お店の人の声くらいで、歩く人たちからは、ずっと外国語。感心するやら、驚くやらで、秋の京都を満喫した。
11月某日 浮標 研究室にある日本酒度計とアルコール計の浮標を廃棄することになった。おもりに水銀を使っていることから処分してもらうことになった。ちょっとさみしい感じはするが、割れると危険なのでしかたがない。
11月某日 令和の米騒動 近くのスーパーで大学の農場の米を販売していた。堆肥つくりから取りくんで、減農薬の米。学生や大学の技術職員が作業している。値段が安く、わずか2日で、売り切れていた。かつてないくらいに米の値段が高いことになっているが、酒造りにひびかなければいいがと思う。
10月某日 メジャーリーグ 大谷選手が出ているから、ついついポストシーズンの放送を見てしまう。午前中、メジャーリーグを見て、夜日本シリーズを見る。野球を見ている時間が長い。論文も読まねばならないが、つい見てしまう。
10月某日 プロ野球ドラフト会議 「よかったですね」とあちらこちらで言われた。3年連続最下位から脱出できるだろうか。アマチュア最強左腕と二番目の左腕の交渉権を得られたのは大きい。即戦力としての期待が高いので、来シーズンが今から楽しみになってきた。
10月某日 発酵食品展示会 愛知県国際展示場で開催されたFOOD STYLEの「発酵食品ワールド」に出展した。研究室に「食品発酵学」という名前をつけている研究室なので、ぜひ、名前を宣伝しなければと思った。これまで、関係してきた発酵に関することを紹介すると同時に、発酵業界への人材を出すというようなところでも三重大学をアピールする必要もあるかと思う。三重大学の卒業生の方が、学部を超えてブースに立ち寄ってくれた。ここからはじまる縁のようなものもあるかもしれない。
10月某日 講座スポーツ大会 こうしてスポーツ大会に出るのも、これが最後。このスポーツ大会にしか、はかないアディダスの体育館シューズを、まず家で探すことからはじまる。コロナで中断もあったが、久々に、研究室に優勝トロフィーが帰ってきた。「先生のために、がんばりました」と言われると、嬉しい感じ。チームで、ミスをカバーしながら、ひとつになって、みんなで頑張ることは大事だと痛感する。
10月某日 新商品 某社に勤める卒業生が開発担当だったという新商品を、コンビニでみつけた。買わないわけにはいかないかと購入した。こうして店頭に並んでいるのを見るだけで、ちょっと嬉しくなる。
10月某日 ジュニアドクター育成塾 今年もデンプンをアミラーゼで分解する実験。この酵素活性測定法は、国税庁の所定分析法にある麹菌の酵素力価を測定する方法をもとに、小学校高学年でもできるように改良したもの。測定したT%値を100から引いた値を縦軸に、横軸に時間(2分間隔)を取ると、きれいな直線になる。この傾きがデンプンの分解の速度を表していると、わかってもらえるといいかな。温度や、添加する酵素量を変えるとどうなるかを体験してもらって、色の加減を数値化してグラフに書けることが理解してくれたら満点です。
10月某日 曼珠沙華 曼珠沙華の花が、例年よりも10日くらい遅れて満開になった。
10月某日 定期券 28年間購入して来た近鉄の通勤定期券も、今回の購入が最後になるかな。もう定期券を買うこともないかと思えば、これも想い出になるのかもね。それにしても、金額が上がったのには、ちょっと驚く。
10月某日 アクセプト 共著でもなんでもないが、かつての留学生が、母国で書いた論文がアクセプトになったと連絡をくれた。研究室で同じ時間を過ごした学生が、活躍していると連絡をくれるのは、こころが暖まる。
9月某日 前半終了 振り返るとあっという間の半年だった。とくに、済んだことは、すぐに忘れていることが多いので、半年を振り返っても、遠い過去のような感じがしてしまう。残すところ6ヶ月、きっとあっという間にやってくるだろうね。
9月某日 学会支部例会 農芸化学会の中部支部例会に参加した。院生もポスターを発表した。他大学の学生を含め、研究の内容を語ってくれる姿が頼もしい。なかには、先生に言われたとおりしかできていないとか、自分で考えていないなと思わせるものもあったが、総じて自分の研究にしっかり取り組んでいる感じで、こちらにも元気がもらえた発表が多かった。
9月某日 アクセプト 何回聞いてもよい響きだ。投稿した論文が、受理されることを accepted という。懸命に実験をした学生の執念が実った感じだ。受理された論文は、いまではオンラインで公開される。世界中の人たちが、その論文を読むことができる。どこかの誰かが、この論文を見て、新たなアイディアが生まれたり、論文で明らかになったことを、次に展開してくれるといいかなと思う。研究室は、すごい機械があるわけでもなく、豊富な研究費があるわけでもない。それでも、考えて、地道に積み上げた実験の結果が、こうして世に出るのは、本当に嬉しいことだ。
9月某日 立浪監督辞任 3年連続最下位では、言い訳できないかな。低迷しているチームを、ミスタードラゴンズ、立浪和義が立て直して優勝する。そんな姿を思い描いていただけに、残念としか言いようがない。
9月某日 應用黴菌學 父親の書物のなかに、「應用黴菌學」という本がある。ケミストだった親父が、なぜこの本を購入したのかは、今となっては謎でしかない。この昭和9年に書かれた本を開いてみると、とても興味深いものがある。いわゆる戦前の日本の微生物に対する知識がどのようなものであったのかがよくわかる。そのなかで、好熱性繊維素分解菌として、Clostridium thermocellumが紹介されている。「好気性桿菌で」という記載は間違っているが、「発育の適温は55-65℃、繊維素を分解し、炭酸ガス、水素の他、酢酸、蟻酸、及び少量の乳酸等を生産する」と書いてあるので、間違ってはいない。たまたま、出版社から依頼されていた C. thermocellumのセルラーゼについて解説文を書いていたところだった。90年前の本に出ている菌をいまだに研究しているというのも感慨深い。
9月某日 敬老の日 TVニュースでは65歳以上の高齢者の人口割合が、過去最高になったと報じている。これから毎年、そうなるよなと思う。まもなく仲間入りだと思うが、自分が高齢者だという自覚がない。しかしながら、シルバー人材センターや、老人会の誘いがくるようになって現実味をおびてきた。
9月某日 同窓会総会 生物資源学部同窓会の総会が開催されました。かれこれ、10年近く、学内代表として、同窓会にかかわってきましたが、今回の総会をもって御役御免になりました。先輩諸氏からすると物足らない代表でしたが、なんとか、次の世代にバトンを渡すことができました。
9月某日 授業アンケート 結果が出せなかったの一言。満足度、学修時間ともに、前年度を大きく下回った。コメントを見て思うことは、学生が答えをもとめる傾向にあること。課題についてのクレームがいくつかあり、正解がわからないとあったが、正解などもともとない。いかに論理的に説明をするか、いかに情報を集め,統合して、読む側に伝わるように説明するかを求めているが、結局、どこかのHPのコピーとかでおわっていて、なにも考えていないし、説明をしようという意志が見えていない。試験問題で、次の語句を説明せよというような問題で、何を書いていいかわからない、説明の仕方がわからない・・・・科学も重要だけど国語の問題なのか。いずれにしても、結果が出せなかった落胆は大きいが、挽回のチャンスはもうない。
8月某日 台風10号 PCR実習をはじめたのが2004年でしたが、2004年には、もうひとつ、大雨という事件がありました。この大雨、津市で、11時から、98、83、90ミリという、とんでもない雨が降り、1日に雨量として観測史上初の401ミリという豪雨でした。それから20年、それに匹敵するような雨が降りました。台風はずっと九州にあるのに、雨がずっと降っていました。降り始めからの雨量は、600ミリを超え、平年の津の8月の平均降水量144ミリの4倍近くに達した。川がかなり危険な状態でしたが、このあたりでは、大きな災害がなかったのが幸いでした。
8月某日 放送大学セミナー 今年3回目のセミナーを行った。セミナー後もいろんな質問が出て、この分野に興味をもってもらえているようで、嬉しかった。微生物学は、高校まででほとんど教えられていないので、一般の人にとっては、不思議な世界なのかもしれない。
8月某日 高大連携 今年も高校生のPCR実習を実施した。これも、随分と長くやってきた。一番はじめは、2004年の松阪高校からはじまっていて、これも20年続けた。当初は、高校生が大学で実験をするということで、マスコミもめずらしかったようで、新聞各社の取材や、TVでの放映もあった。今では高大連携は当たり前になった。この20年で、DNAポリメラーゼの性能もずいぶんとよくなった。かつては、口腔スワブからのDNA回収にカラムをつかった精製キットをつかっていので、相当な時間をかけていたが、今では、10分のアルカリ抽出と、遠心分離ですむので、30分もかからない。かつてDNAポリメラーゼの反応は、1kbあたり1分で、プログラムをくんでいたが、いまでは、1kbあたり1秒で設定できるので、PCR反応も40分で終わる。実験時間は短縮されたが、内容はずっと同じで、第一染色体のVNTRの増幅という実験だが、今では、高校生物の図説にも出ている。
8月某日 南海トラフ地震臨時情報 本当に出るんだと思いました。確かに想定震源域での地震でしたので、これが横に来ると、どかん、と大きな地震になると考えることができます。ただ、この情報による損害も出るので、気象庁は出せるのかと思っていましたが、現実に出ました。おかげで、予定していた大学のオープンキャンパスは、中止となりました。確率は低いものの、もしもを考えると、こういった決断もやむをえないかなと思います。近くのスーパーでは、ペットボトル入りの水が、箱単位で飛ぶように売れていました。
8月某日 定期試験 こうして定期試験をするのも、これで最後かと思うと感慨深いものがある。採点をしながら、やはり上手くは伝わらないものだと感じる。授業中にも、「これは試験によく出ています」のような言葉を入れているのですが、なかなか対応してくれない。誰かが過去問の模範解答をつくっているのか、多くの学生が同じ答えを書き、間違っているという不思議な現象が起きている。マスでの教育は限界かなと思うが、それでも、なかには光る学生も数名いて、答案に勇気づけられたりする。
7月某日 感染 呼吸器系のウイルスに感染した。新型コロナの抗体検査は、ネガティブだったが、症状的には、近いので、コロナだったのかもしれない。忙しい時に、困ったことになったが、とりあえずは、静かにしているしかない。熱は、2日でおさまったが、咳がとまらず、苦しい思いをした。1時間ごとに体温をはかっていたら、体温計の電池が切れてしまった。幸い、オリンピックが開幕していたので、TVを見ながら過ごすことはできたが、学部最後の授業をオンラインにせざるをえず、ちょっと残念だった。
7月某日 講座縦コン 講座の3年生を招いて、縦コンが盛大に行われた。まあ、彼等が4年生になるときには、もういないので、話しに来る学生もわずかだったが、そんななかでも、少しの3年生と話しができてよかった。
7月某日 北里柴三郎先生 やっと新札が回ってきました。新札が発行されてから、2週間以上たったが、やっと北里先生に会えたという感じでした。
7月某日 大学賞のお祝いの会 先にいただいた大学賞のお祝いの会を開催していただきました。前理事、現理事にも参加いただき恐縮しました。つくづく多くの皆さんに支えられてきたと思いました。
6月某日 バンテリンドーム いきなりHRを打たれて、反撃できずに、終わりました。さすがに、3年連続最下位では、監督の能力をうたがわざるをえないことになりそうです。どんな世界も、結果をいかに残すか、与えられた要素が決まっているとしたら、それを最大限に活用するにはどうすべきか。プロの世界は結果がもとめられ、結果がでなければ失職するし、活躍できる時間も短い。幸い、我々は、もう少し時間を与えられているが、基本は同じ。与えられた要素のなかで、最大限に活用するにどうすべきか、プロスポーツから学び、考えることはたくさんあるように思う。
6月某日 交流戦も終わり、気がつけば、いつも位置に転落。なかなかうまくいかないもんですね。
6月某日 同期会 大学の同期会に参加しました。当時の担任の先生、今でいう就学カウンセラーの先生のお墓に、皆で挨拶に行きました。皆無事に卒業できたのも先生のおかげですので。その後、大阪で宴会をしてから、移動して、京都に宿泊しました。翌朝、平安神宮を参拝し、ちょうど見ごろという菖蒲園を散策しました。平安神宮をおとずれるのは、なんと、小学校の修学旅行以来、実に、53年ぶりに境内に入りました。当時の記憶は、宿で、枕なげしたとか、平安神宮のあと、比叡山に登ったとか、バスの中で、みんなで歌を歌ったとか・・・、そういえば修学旅行について書いた「詩」が、学年便りに掲載されて嬉しかった。
6月某日 納豆のネバネバ 今年も微生物学の課題で、納豆のネバネバは何でできているか、という課題を出しました。85名の提出者のうち、84名がポリグルタミン酸のことを書いてくれました。若干1名が、ムチンと書いていましたが、多くのHPで修正がされていることが確認できました。
5月某日 大学賞 推薦をいただき、三重大学賞をいただいた。高等教育創造開発センターの部門長、教育担当の学長補佐、副学長の時代に行ってきた「教学マネジメント体制」の整備を評価していただきました。これは、私個人というより、理事をはじめ、センターの先生方や事務方といっしょにやってきたことですので、皆さんの成果を代表としていただくという思いでした。地元TVのニュースでも放送され、自分をTVで見るのは、ちょっと恥ずかしい感じでした。
5月某日 歯医者 親知らずが悪さをしているので、抜きましょうと、歯医者さんに言われてしまった。手術になるので、大きな病院の紹介状を書きますと言われた。かつて、親知らずのひとつを抜いたとき、たいへんな目にあったので、なんか尻込みしてしまう。とりあえず、授業が終わるまで、まってもらうことにした。
5月某日 環境展 久々の東京出張というか、コロナ後はじめての東京じゃないかな。東京ビッグサイトも、本当にひさしぶりな感じでした。いろいろなことが、コロナ禍を経て変わったと思いました。いつも通勤でつかっている定期のカードで、新幹線にも乗れた。電子化は益々進み、切符なんて概念がなくなるんじゃないかと思えるくらい、新幹線の指定席から、ホテルの予約も全てオンラインで自宅からできた。まあ、当たり前といえば、そうなのかもしれないが、コロナ前は、出張の時、旅行会社から切符が来ていたので、ちょっとだけ面食らった感じ。現職の国会議員の先生も、三重大学のブースに来てくれた。環境に取り組む大学としてのPRは重要かなと思う。
5月某日 VTR収録 某地元テレビの番組のなかでのコメントを収録した。多少セリフをかんだが、編集でなんとかなるそうで、一発OKになり、よかった。
4月某日 円安 円安にはどめがかからず。円高になる要素もないので、当分続きそうだ。資源や食料のほとんどを海外に依存している日本では、円安は生活を直撃することになるんだけど、みなさん、結構呑気な感じです。
4月某日 SSH校の発表会への参加 高校時代に研究ができるのは、羨ましいかぎりだ。いろいろな研究発表があって面白かった。指導する先生方もたいへんだったとは思うが、大学も将来への先行投資くらいに考えて、SSHへのサポートにインテンシブを与えてくらたら、きっともっと多くの先生がかかわれるのではないかと思ってしまう。そうした活動のなかで、ちょっと光る生徒を推薦入試で入れるというようなことができるといいなとも思う。もちろん、その生徒が、うちの大学に来たいと思ってくれていたらの話しではあるが。
4月某日 学生の書いた論文がアクセプトされた。もう少し早くアクセプトが出ていれば、学長表彰の対象になったのにと、ちょっと悔しい思いもある。
4月某日 首位 ドラゴンズが、実に2016年以来の単独首位。もちろんまだ4月、まだ他球団と一通りも当たっていないけど、それでも「首位」という言葉がなんともいえず、心地よく、10勝、一番乗りというのも嬉しい。3年目の立浪ドラゴンズ、今年は違うというところを見せてほしい。
4月某日 微生物学 教員生活の最後の学部15回の講義がはじまりました。運悪く在学生健康診断の時間がかぶってしまったため、健康診断に行く学生が目立ちました。気合い入れていきます。
4月某日 放送大学 今年度から、放送大学の客員教員を兼務するようになりました。今後、セミナーや公開講演会などを通して、「微生物」を語っていきたいと思っています。
4月某日 オリエンテーション2日目 教育的インターンシップや、三重創成ファンタジスタ資格の話をして、これで、前年度教務委員長の仕事は、すべて終了。ここからは、新年度の教務委員長の仕事になる。応援団のエールを毎年、校舎の中庭でやってもらっているが、昨年はほとんど1年生が集まらなかった。今年は、たくさんの1年生が応援団のエールを聞いていた。この違いは、いったい何なのか。学年がかわるだけで、そんなに変わるものなのか。ちょっと不思議な感じだった。
4月某日 オリエンテーション 新1年生への履修指導。前年度の教務委員長が例年することになっているので履修指導を行った。いきなり情報が過多な感じはするが、すぐに共通教育の時間割を作成しないといけないので、まずは、履修システムへのログインができる状態になってもらわないといけない。コンピュータをもってきてもらったが、多くの学生が、電源コードをもってきていなかった。最近のコンピュータは電池が長持ちするんだと思っていたら、ある学生が、高校では構内で充電してはいけないことになっていたとか電源コードを持っていけなかとか。大学は講義室にも、ラーニングスペースにコンセントを用意しているので、勉強にはいくらでも使ってもらっていいんですけどね。
4月某日 入学式 昨年は、桜がもつかどうかの心配をしていたが、今年は、桜の開花がちらほらだった。大学院生(博士前期課程)の学生に履修指導をした。大学院は、学部とは、ちょっとちがっているので、そのあたりを確認した。新1年生も元気に入学式に出ていた。大学の1年がはじまった感じだ。
4月某日 辞令交付 大学教員生活の最後の1年がはじまりました。
3月某日 紅麹 マスコミで微生物の話題が出るのは食中毒や健康被害。紅麹(モナスカス属)は、いわゆる麹菌(アスペルギルス属)とは異なり、属より上の科で、異なっていますので、麹菌ではありません。麹を原料にした、お酒やみりん、酢、醤油、味噌といったものに、風評被害がでなければいいがと心配です。
3月某日 定員割れ 中部地方の私立大学の61%が定員割れというびっくりの記事が新聞に出ていた。思ったよりも少子化の影響は早く出てくるかもしれない。
3月某日 こども大学 伊賀研究拠点で開催されたこども大学に参加した。和紙と洋紙の切断面を顕微鏡で観察すると、和紙のほうが繊維が太いし、切れにくい。地域でも和紙の原料であるミツマタの栽培を増やしているとか。伝統的なものに科学的な根拠を入れて残していくことが重要かなと感じた。
3月某日 学位記授与式 今年も、4年生6名と、大学院前期課程3名が、研究室を巣立っていった。ちょっとお天気が悪かったけど。みんな元気そうで何より。
3月某日 オープン戦首位 ソフトバンクと並んで、オープン戦首位というドラゴンズ。ちなみに、オープン戦を勝ち越した年は、かならずAクラスという過去のデータがある。期待満点で、開幕を迎えたい。
3月某日 退職記念祝賀会 今年度は、定年退職や早期退職で8名の先生方が、ご退職になり、その祝賀会が、実に4年ぶりに行われた。年長者ということで、乾杯の音頭をとった。コロナ禍とかいろいろなことがあり、先生によっては、生物資源学部になる前に採用になった先生もおられ、歴史を感じた。
3月某日 中選手追悼試合 子供の頃によく聞いた「1番センター、中、背番号3」というアナウンスが、強烈に残っている。中選手の追悼試合に、バンテリンドームにでかけた。オープン戦とはいえ、昨年の日本一の阪神に勝ったのはよかった。昨シーズンは、ドームにでかけた全ての試合で、負けたので、オープン戦とはいえ、ちょっと嬉しい。
3月某日 後期日程個別学力試験 無事に終わってほっとする。モチベーションの高校生に来てほしい。
2月某日 前期日程個別学力試験 次年度からカリキュラムが変わり、1学科制になることで、入試の予想が難しくなっている。果たしてどんな学生が来てくれるのか、楽しみではあるが、関われるのが、最初のオリエンテーションくらいかな。カリキュラムの変更で、1年生の授業が減ったので。
2月某日 「雲外蒼天」 地元伊勢鉄道が、地震で被害のあった「のと鉄道」を応援する鉄印を販売すると聞き、さっそくでかけて購入した。鉄印に書かれた「雲外蒼天」の文字がしみる。
2月某日 博士課程集中講義 久々の集中講義でした。さすがに、4コマ連続は、体力的にきびしくなってきました。それでもさすがに博士課程の学生さんは、対応がすばらしく、授業も楽しくできました。
2月某日 卒業研究発表会 今年の4年生は、コロナ禍で、1年のときは大学に登校すらできず、2年生の授業もほとんどがオンラインだった。研究室の6名の4年生も、しっかりと発表してくれた。ちょっと残念だったのは、発表会後の打ち上げの会。コロナ前は、けっこうな盛り上がる会だったけど、今年は4年生の参加がすくなく、参加している教員のほうが多いくらい。それでも修士の学生がたくさん参加してくれたので、久々に楽しい時間を過ごす事ができた。
2月某日 修士論文発表会 今年の修士2年の学年は、大学1年生からの担任だったので、こうして立派に発表している姿を見ると感動する。コンピュータのファイルには、彼等が大学1年の時につくった自己紹介のPDFが残っているが、高校時の制服や入学式のスーツ姿の写真が多い。あどけない学生だったが、6年経って、タンパク質の結晶構造を解いたり、次世代シークエンサーをフル活用してり、複雑な化合物を合成したり、新しい分析方法を提案したり、膨大なデータを操りプログラムを書いたり、さらにこうした研究を英文の論文にして投稿したりして、驚くばかりの成長を見せてくれた。なにより、様々な質問をぶつけてくる教員に対して、しっかりと受け答えでき、議論できている姿が、なんとも頼もしい。6年前は、まったく想像できなかった。学部4年の卒論はコロナ禍でオンラインの発表会だったけど、今年は大講義室で元気に発表してくれ、プレゼンも立派なものだ。成長をみせてくれた嬉しさ半分と、彼等がいなくなるさみしさ半分かな。
2月某日 産学官連携セミナー in 伊賀 今年のテーマは、AI(人工知能)でした。人工知能が勢いを増しており、人工知能でなくなる職業なんていうのが、話題になっているが、今回の講演で聞いたところでは、人工知能vs人、ではなく、人工知能を使いこなせる人vs使えない人、ということだそうだ。かつて、90年代のはじめ、コンピュータやメールが入ってきたとき、タイプできない人やメールに対応できない人がいたが、同じようなことかもしれない。時代は変わる、変わる時代にどう対応するか。
2月某日 修論審査 博士前期課程の学生さんが増えたので、審査件数も多くなった。研究室が違えば修論のスタイルも違うし、引用論文の書式もいろいろ。苅田研究室の卒論や修論は、米国微生物学会誌の書式と同じにしている。かつては、「フェノクロ、エタ沈した」なんて、方法に書く学生もいたが、今では、皆な、同じような文言になってしまっている。自分の言葉で書くよりも、失敗を恐れる世代なのかな。
2月某日 プロ野球キャンプイン 今年こそ、今年こそ、打つ方をなんとかしてほしい。
1月某日 工場見学 何回参加しても、これほど楽しいものはない。どうして、学生は嫌がるのかがわからない(レポートを課しているからか)。企業がどんな活動をしているのかは、実際に見てみないとわからないし、普段目にしているものが、どのような過程でできているのかを知るのは、いろいろなことに役に立つと個人的には思う。せっかく大学からバスで行けるのだから、もう少し受講者が多くてもよさそうな気がする。机の上の勉強や実験も大切だが、何を見ているか、何を経験しているかは、自分の幅を広げるためにも重要だという気がする。工場見学に行けば、いろいろな企業を見ることができる。規模感や、従業員の様子や、機械類の大きさ、技術など、感じることはいっぱいあるはずだ。就職説明会でブースで話しを聞くよりも、よほど多くの情報を得ることができると思う。たとえ就職したいと思っていない分野であっても、その製品なり商品が、どんな検査を受けて、あるいはどんな装置で作られているかを目でみるだけで、価値があるように思うけどね。
1月某日 博士課程の発表会 博士課程の研究は、分野がちがっていても聞きごたえがありますね。どのように考え、どのように研究をプラニングし、何をどのようにすれば、自分の考えが証明できるか、あるいは、ある現象を観察した上で、その現象の法則性というか、規則性を明らかにしていく。生物資源には、いろいろな研究があり、自分の分野以外の研究もそれなりに楽しめる。ちょっと残念なのは、学部学生が大学院の発表会に来てくれないことだ。こんなに楽しい世界があると、先輩たちが語ってくれているのに。
1月某日 大学院入試 大学院の二次入試がありました。博士前期課程から後期課程に進学する学生さんの入試も含まれています。博士をもっていないと就けない仕事もありますし、博士をもつことで優位になる職業もあります。個人的には、どうせ一度の人生なので、もし研究することが好きなら、好きな事を思いっきりしてみてはとは思います。ただ、お金はかかります。それでも、学術振興会とか、最近は、博士課程に様々な優遇制度もありますので、今は、ねらい目なのかもしれません。
1月某日 原著論文の受理 かつて研究室に来ていた留学生が、祖国にもどって、書いた論文が雑誌に受理されたとメールが来た。ちょっと嬉しいかな。コロナ禍があって、研究室への制限や、サンプルの入手ができないことなど、かなりきびしい状況があったなかでも、がんばっている様子に、安心した。
1月某日 大学共通試験 大学にとっては恒例行事です。受験生もたいへんですが、大学教員もけっこう大変です。三重大学は、全国でも受験者数の多い大学のひとつですが、それでも、年々受験者が減少していることが、よくわかります。思っているよりもはやく18歳の大学受験者人口は減少しているかもしれません。かつての国立大学のように授業料が安いわけでもありませんので、大学を選択しない場合もあるかと思います。これからは、いかに学生を確保するかというところが、大学の経営にとっては重要になってくるのではないかと、感じてしまう共通試験です。
1月某日 新年あけましておめでとうございます。今年こそよい年になるように願っています。元旦そうそう緊急地震速報で緊張が走りました。名古屋の親類の家に集まっていたのですが、中層マンションで、結構な揺れでした。元旦の地震ということで、2024年は、ちょっと不安なスタートとなりました。教員生活も残すところ1年と少しになります。最後の1年となりますので、1日、1日を大事にしていきたいかなとも思います。今年もよろしくお願いをいたします。
2021年分はこちら 2020年分はこちら 2019年分はこちら
2018年分はこちら 2017年分はこちら 2016年分はこちら
2015年分はこちら 2014年分はこちら 2013年分はこちら
2012年分はこちら 2011年分はこちら 2010年分はこちら
2009年分はこちら 2008年分はこちら 2007年分はこちら
2006年分はこちら 2005年分はこちら 2004年分はこちら
2003年分はこちら 2002年分はこちら 2001年分はこちら
トップページへもどる